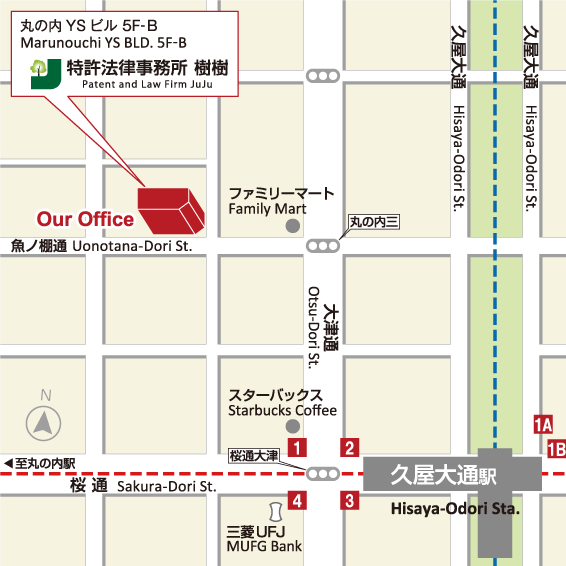資料はこちら
【民事訴訟or刑事訴訟?(1)】
今回の調査研究の中心的なテーマは、タイで権利行使を考えるときに民事訴訟、刑事訴訟のうち、どちらをどのように活用するのがよいか?という点であった。
タイでは刑事訴訟を第一に考えるべきと書かれている文献も多数ある。確かに、統計上もタイでは刑事訴訟が中心となっているが、これは、タイのDIP(知的財産権局)が刑事手続を推奨したことが一因であるとの情報もある。
また、民事訴訟は刑事訴訟よりもコストが高く、期間もかかるとの見解もある。しかし、これも事案によりけりである。民事訴訟では、翻訳料が費用の少なからぬ部分を占めるが、CIPITCでは、訴訟の書類や証拠等を英文で提出できる特則の適用があるため、これを活用することにより、翻訳料、ひいては訴訟の費用を低減できる可能性がある。また、刑事訴訟は早いという点についても、事案によっては、検察官が証拠を精査するのに時間を要し、捜査が終了してから起訴まで1年以上を要することもあるようだ。このように考えると、費用や所要期間に基づいて単純に民事訴訟か刑事訴訟かを判断することはできないように思われる。
【民事訴訟or刑事訴訟?(2)】
これは、今回の調査研究に基づく一つの提案であるが、やはりタイでは刑事訴訟を優先するのが良いと考える。タイでは、共同原告という形で権利者が刑事訴訟に関与することができ、また刑事訴訟での経済的補償も認められているからである。刑事訴訟を優先することで、これらの特徴を活かした対処を行うことができると考えるのである。
まず、権利者は、刑事告訴し、共同原告として検察とともに刑事訴訟を提起する。そして、この刑事訴訟内で、侵害によって受けた被害の回復も請求するのである。これが認められれば、民事訴訟で損害賠償請求を行ったのと同じ効果が得られる。しかも、警察・検察官と協力して進めるから、捜査を通じて、侵害や損害の立証に必要な証拠を収集することもできる。
ただし、刑事訴訟のみでは十分でない場合もある。刑事訴訟で請求した被害額のうち、一部が認められないこともあるからである。また、刑事訴訟において有罪判決が下されるためには、侵害者が侵害行為を故意に行っている必要があるが、事案によっては、故意とは認められないこともあるからである。
このような場合には、その後、民事訴訟を提起すればよい。刑事訴訟で認められなかった不足分の損害賠償の支払いをもう一度求めるチャンスが得られることになるし、故意で無罪と判断された場合でも、「過失」ありと認められ、損害賠償請求は認められる可能性もある。しかも、刑事訴訟で警察・検察によって収集された証拠は、民事訴訟でも活用できるのである。
このように、タイでは刑事訴訟を優先的に進めながら、民事訴訟を補足的に活用するという方法がよさそうに思われる。なお、同じ侵害事案に対して、刑事訴訟と民事訴訟の双方が提起された場合、裁判所は一方の判決が出るまで他方の審理を停止しておくとのことである。民事訴訟、刑事訴訟のいずれを先に進めるのかという点については、確認できなかった。
(続く)