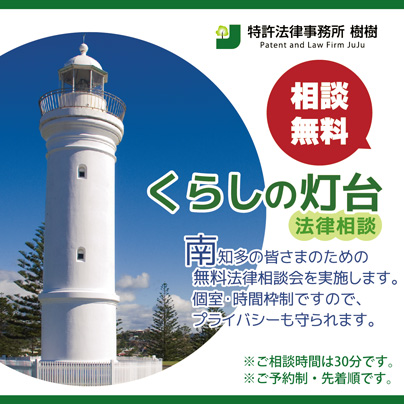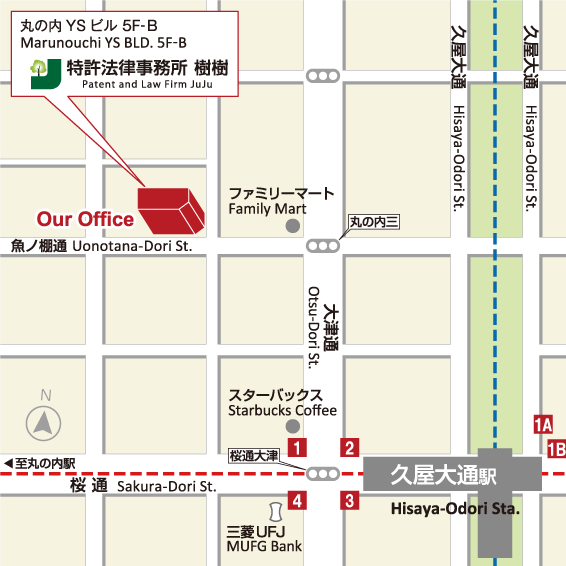昨日(平成26年1月31日)、ヒルトンホテル名古屋において、弁理士会東海支部開設日記念「知的財産セミナー2014-タイの知財丸わかり~タイにおける特許、商標、権利行使、およびインドネシアの知財制度概要~-」が開催されました。企業の方、弁護士・弁理士など300人以上の方にご参加いただきました。ありがとうございました。
セミナーは、イントロダクション(タイ・インドネシアの知財動向)、特許セッション、商標セッション、権利行使セッションの4部構成です。それぞれ、弁理士会東海支部の東南アジア委員会委員によるプレゼンテーション、およびタイから招いた3名の弁護士とのQ&Aで構成しました。
私は、最後の権利行使セッションで、講師を担当いたしました。持ち時間が45分でしたが、昨年10月のタイ視察を経て、是非、伝えたいと考えていたエッセンスの部分は、お話しできたと思っています。もっとも、お伝えしきれなかった部分も、たくさんありますので、後日(2月下旬ころになる予定です)、数回に分けて、解説記事を、この樹樹つなぎに掲載したいと思っています。よければ、是非、ご覧ください。