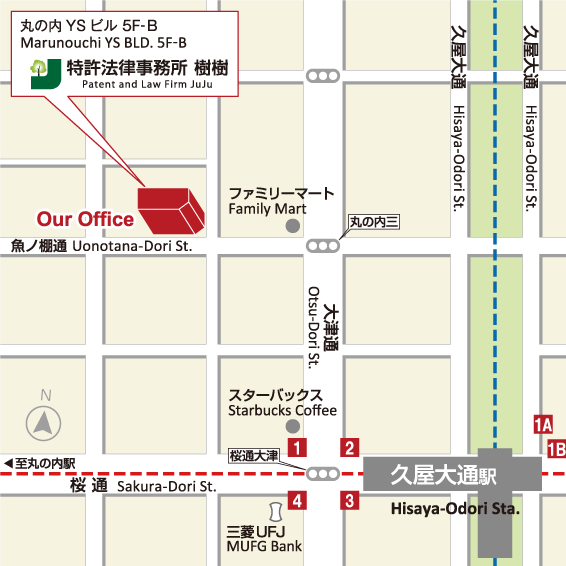資料はこちら
【抗がん剤製法特許侵害事件(3)~権利範囲の解釈】
抗がん剤製法特許侵害事件でCIPITCと議論をした点がもう一つある。特許権の権利範囲の解釈についてである。
タイの特許法は、日本と異なり、均等論の適用を明文で規定している。つまり、タイ特許法36条の2では、「特許発明の保護範囲は、クレーム中に特に記載がなくとも、…クレームに述べられているのと実質的に同じ特性、機能及び効果を有する発明の特徴まで拡大される」と規定されているのである。
この規定は、均等論の適用について明文化したとも読めるが、同時に、クレームの解釈方法について規定しているとも読める。後者の解釈に立てば、クレームの文言を厳格に解釈する必要はなくなり、均等の範囲を含めた幅を持った解釈が許されることになる。
ディスカッションにおいて、CIPITCからは、「クレーム解釈について確立された判断手法がある訳ではない」との回答を得ており、上述の疑問点については明らかにはならなかった。しかし、CIPITCは、「均等論については権利者がそれを主張したときに考慮する」とも述べていた。このことから考えると、クレームについて日本と同様の文言解釈を行った上で、権利者が主張すれば均等論についても考慮するという2段階の権利解釈となるのであろうか。この場合、法律において均等論が名文で規定されているのに、権利者が主張しないときには、それを考慮しないという解釈が許されるのであろうか。
このように、クレームの権利範囲の解釈方法についても、まだまだ問題点が存在するように思われ、今後、種々の事案が表れるごとに大きく変遷していく可能性もあると思われる。
抗がん剤製法事件では、CIPITCと最高裁で判断が異なった。被告の製法では「アセトン」を使用しており、原告の「アルコールを使用する」というクレームの均等範囲に属するか否かの判断が、両裁判所で異なったためである。しかし、残念ながら、調査した範囲では、判断が異なることとなった理由の詳細は、わからなかった。
【権利無効の抗弁?】
日本における特許権の侵害事件では、対象となっている製品等が特許権の権利範囲に含まれるかという属否論と、特許が無効であるとの抗弁とが主張される。タイにおいても、無効の抗弁が主張されるのであろうか?これがCIPITCでの3つめのディスカッションのテーマであった。
結論として、タイでは、訴訟において、「特許無効の抗弁」を主張することはできないとのことである。タイでは、特許の有効性については、権利取消訴訟で争う必要があるのだ。従って、訴訟において特許の有効性を争いたい場合には、権利取消訴訟という別訴を提起する必要がある。そして、権利取消訴訟を提起すれば、裁判所は、侵害訴訟と権利取消訴訟とを併合して審理するようである。仮に権利取消が認められると、それはその訴訟限りの効果ではなく、対世効を有することになる。
もし、被告が、権利取消訴訟を提起せずに、侵害訴訟の中で特許の無効を主張したとしても、裁判所は、あくまでも権利は有効に成立しているとの前提で判決をする他ないとのことである。タイにおいて特許の有効性を争う場合には、注意を要する点である。
(続く)