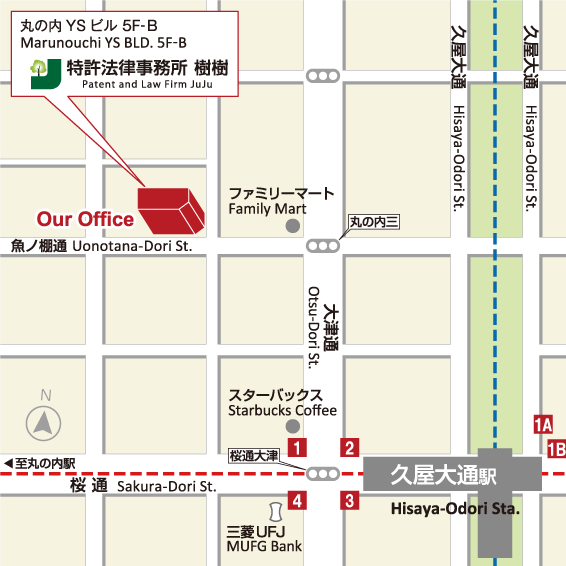先日、志村けんさんが、コロナウイルスに感染してお亡くなりになりました。ご冥福をお祈りいたします。私は、まさにリアルタイムでドリフターズを楽しんでいた世代で、志村けんさんのギャグにも随分と楽しませてもらいましたので、そのことを書き始めればキリがないのですが、今日は、別の話題に触れたいと思います。
“志村けん“の手話は「アイーン」? ろう者が「志村さんに救われた」と語る理由という記事を読みました。あの「アイーン」のポーズが、手話では、「志村けん」という意味で用いられているというのです。他にも、加藤茶さんや、ビートたけしさんを表す動作もあるとのことです。
なるほど、こう考えると、一つの動作が、特定の人物などを表すトレードドレスとして機能することもあり得るのですね。古いところでは、ピンクレディーならUFOのポーズ?、マイケルジャクソンのムーンウォーク?、少し近いところでは、DAIGOのウィッシュ?(まだ古いですか?)などなど。
ところが、こうした動作について、知的財産権としての保護は、なかなか難しいというのが現実です。パッと想像つくのは、著作権です。しかし、ごく短いポーズに対しては、著作権は認められないという考え方が主流なのです。これらに著作権を認めてしまうと、日常の動作に大きな制約が生じかねないからです。日本では、フラダンスの動作を著作権で保護した判例がありますが、その事件も、フラダンスの短い一つの動作のみを保護した訳ではなく、曲一連の動作を対象としていますし、しかもフラダンスには動作に一つ一つ意味があるという特殊な事情もある事件です。
では、商標権?確かに、商標登録も、近年、動きのある商標など、随分と対象は広がってきました。しかし、商標は、あくまでも文字、図形、立体など何かに付けたり表示されたりするマークを対象とするものなので、人の動き自体を商標として登録することはできません。その動きを表す写真やイラストなどを商標登録することはできますが、それで、動き自体を保護できる訳ではありません。
となると、不正競争防止法ということになります。不正競争防止法では、周知とか著名であることが必要とされるのですが、志村さんのアイーンのように、これほどよく知られていれば、周知または著名という要件は満たすように思います。ただ、不正競争防止法も、その保護対象は、「商品等表示」という用語で表されており、やはり「表示」なのです。人の動作が、この「表示」に該当するのか?議論になるところです。
まだまだ動作に対しては、いろいろと検討の余地があるかも知れません。
もっとも、志村さんは、自分のギャグをたくさんの人がマネることを、喜びそうな気はしますけど。
“志村けん“の手話は「アイーン」なんだ!(弁理士・弁護士 加藤 光宏)
- 2020年 4月 02日
親族間のトラブル(相続・離婚)
- 2018年 11月 01日
相続税がかかる目安は?
相続税は「3,000万円+600万円×法定相続人の数(妻、子など)」以上の額の相続財産がある場合に、納付する必要があります。
(例)妻と子2人が相続人の場合
4,800万円(=3,000万円+600万円×3)
例の場合、4,800万円以上の財産をお持ちであれば、お亡くなりになった際、相続人の皆様に相続税がかかる可能性があります。そのため、自宅が持ち家の場合や多額の預貯金がある場合などには、相続税がかかる可能性は高いです。
遺言書を作成することは必要?
遺言書は、亡くなられた後にご家族へ意思を伝えることができる数少ない手段の1つです。現に、遺言書があったことで、相続に関するトラブルを未然に防止することができたという事例もよく見られます。そのため、財産の多少に関わらず、遺言書の作成を検討されることをお勧めします。
また、遺言書作成の準備として、現在の財産状況を把握することとなり、その過程で、相続税対策をする必要があるか否かを検討することができます。
なお、遺言書の方式は法律で決まっており、その方式に従っていないものは有効なものとして扱われませんので、ご注意ください。
離婚にはどのような方法がある?
離婚する方法は、(1)協議離婚(夫婦での話し合いによるもの)、(2)調停離婚(家庭裁判所の調停手続(話し合い)によるもの)、(3)裁判離婚(家庭裁判所の裁判手続によるもの)の3つがあります。
離婚のために裁判を起こす前に、調停手続を経る必要があることから、我が国の離婚制度は、話し合いによる円満な解決を図ることを重視しています。
婚姻費用って何?
「婚姻費用」とは、夫婦及びその子供が家庭生活を送るのに必要な費用(いわゆる生活費)のことをいいます。「婚姻費用」は、法律で定められた夫婦間の扶助義務や親子間の扶養義務を具体化したものなので、仮に夫婦関係が悪化し、別居状態になったとしても、離婚をするまで負担の問題が発生し、収入の少ない方(収入がない方も含みます)から収入の多い方に対し、婚姻費用を分担するよう請求することができます。
なお、婚姻費用の金額は、全国の裁判所が運用する大まかな算定方法の基準があり、その基準に則ったうえで個別具体的な事情を踏まえて決定されます。
業務中・通勤中の交通事故について
- 2018年 11月 01日
業務中の交通事故の場合、会社も責任を負う?
労働者が業務中に交通事故を起こした場合、原則として使用者である会社も責任を負います(民法715条)。また、人身事故の場合、自動車賠償保障法の運行供用者責任を負います(自動車賠償保障法3条)。
いずれも、一定の要件を満たせば会社が責任を免れることはできますが、その要件は次のように厳格であり、会社が責任を免れることは非常に困難です。
使用者責任
会社は、次のいずれかを証明しない限り、賠償責任を負います。
(1)被用者の選任および事業の監督につき相当の注意を払ったこと
(2)相当の注意をしても損害が発生していたであろうこと
運行供用者責任
会社は、次のすべてを証明しない限り、賠償責任を負います。
(1)運行供用者および運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと
(2)被害者または運転者以外の第三者に故意または過失があったこと
(3)自動車に構造上の欠陥または機能の障害がなかったこと
通勤中の場合はどうなるの?
労働者が通勤中に交通事故を起こした場合、使用者である会社は、マイカーでの通勤か社用車での通勤か、会社が日常的に車通勤を承認・黙認していたか、会社による駐車場所・ガソリン代・維持費等の供与があるかなどの事情が総合的に考慮されて、使用者責任または運行供用者責任を負う場合があります。
労災保険の適用はあるの?
労働者が業務中や通勤中に交通事故に遭った場合、労災保険を使用することができます。また、自賠責保険は、加入が義務付けられている保険であり、自賠責保険を使用することもできます。ただし、同じ損害項目について、双方から二重に支払いを受けることはできません。
一般的に、過失が大きい場合や過失割合に争いがある場合、労災保険では、過失の程度によって減額されないから、労災保険を使用したほうが有利になることがあります。また、それぞれ限度額が定まっている中、労災保険には慰謝料がないことから、治療が長引くような場合、労災保険を優先させたほうが有利となる場合があります。
印紙税の話
- 2018年 10月 31日
印紙を貼らなければならない書類は何?
印紙を貼らなければならない書類は、法律で決まっています。具体的には、不動産の売買契約書、請負契約書、5万円以上(平成26年3月31日以前に作成したものは3万円以上)の領収書などです。
なお、印紙を貼る必要があるか否かは、書類のタイトルではなく、記載内容全体を踏まえて判断します。そのため、新しく作成した書類や、多数の人にほぼ同じ内容の書類を交付される場合などは、印紙を貼らなければならない書類か否か、念のため確認されることをお勧めします。
ひとまず200円の印紙を貼っておけば大丈夫?
貼らなければならない印紙代は法律で決まっていまして、書類の内容に基づいて金額が決定されます。なお、印紙税は、最低200円から最高60万円までの幅があります。
印紙の貼り忘れたら、どうなるの?
印紙を貼らなければならない書類に、適切な金額の印紙が貼られているか否かについては、税務署の調査対象に含まれます。そのため、税務調査の際、税務署から印紙の貼り忘れや貼るべき印紙の金額が不足していることを指摘されることがあります。
仮に、税務署から適切な金額の印紙が貼られていないことを指摘され、その指摘内容が正しかった場合、貼り忘れた印紙の金額若しくは貼るべき印紙の金額の不足分を追加で納付する必要があることはもちろん、ペナルティとして、貼り忘れた印紙の金額若しくは貼るべき印紙の金額の不足分の2倍の金額を納めることが必要になります。
自分の保管する書類だけに印紙を貼っておけば大丈夫?
印紙税は、書類の作成者に納付義務が課されます。そのため、誰が書類を作成したかが重要なポイントになります。
また、契約書などのように複数人で書類を作成した場合、書類の作成者全員が、全ての書類に対する印紙税を連帯して納付する義務を負います。そのため、書類の作成者のいずれかが保管する契約書に印紙が貼られていなかった場合、税務署は、印紙を貼って書類を保管していた書類作成者に対しても、印紙税とペナルティを納付するよう請求することができます。
したがって、複数人で書類を作成した場合は、すべての書類に印紙が貼られているか否かを確認することを強くお勧めします。
税務調査の話
- 2018年 10月 31日
税務調査の前に税務署から連絡がくるの?
一般的には、税務署側から納税者若しくはその顧問税理士に対して、事前に税務調査をする旨(調査の開始日時、開始場所等)の連絡がなされます。
ただし、税務署側が必要であると判断した場合は、事前の連絡を行うことなく、調査開始日当日に、直接納税者の事務所等を訪問し、調査を開始することもあります。
税務調査対応で気を付けることは?
税務調査は、法律に基づき任意で行われる手続ですので、税務署員が納税者に無断で事務所内の引き出しを開けたり、PCを操作したり、書類の内容を精査することはできません。そのため、税務署側から納税者に対し、必ず調査に関する依頼がなされます。
そこで、納税者としては、税務署側からの依頼内容について、法的な視点で対応する必要があるか否かを見極めることが必要となります。
税務調査後は、必ず修正申告をしなければならないのですか?
必ず修正申告をする必要はありません。
税務調査終了時、税務署側は、納税者に対し、調査結果を説明すると共に、納税者の申告した税額に不足があると判断した場合は、修正申告をするように勧めることができます。ただし、修正申告をするか否かは、納税者の判断に委ねられており、修正申告をする義務はありません。
仮に納税者が修正申告をしなかった場合、税務署側は、不足している税額を納付する旨の命令(「行政処分」と言います。)をするか否かを判断し、命令をすることが必要であると判断した場合、納税者に対し行政処分の通知書を渡します。
納税者は、受領した通知書の内容を精査し、内容に不服がない場合は、通知書に記載された税額を納付することができますし、内容に不服がある場合は、通知書を受け取った日の翌日から3カ月以内に、不服申立をすることができます。
なお、不服申立をする場合でも通知書に記載された税額を納付しなければ延滞税が発生しますので、不服申立が認められなかった場合に備えて、予め通知書に記載された税額を納付しておくことをお勧めします。
高度プロフェッショナル制度について
- 2018年 10月 30日
「高度プロフェッショナル制度」って何?
働き方改革の一環として労働基準法が改正され、職務の範囲が明確で一定の年収を有する労働者が、高度の専門的知識を必要とする等の業務に従事する場合に、本人の同意等を条件として、労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定を適用除外とする制度です。
「高度プロフェッショナル」だと何が変わるの?
高度プロフェッショナル制度の適用を受ける労働者は、労働基準法に定められた次のような規制の適用を受けなくなります。
(1) 労働時間(1日8時間、週40時間)
(2) 休憩(6時間超で45分、8時間超で1時間)
(3) 休日(毎週少なくとも1回の休日)
(4) 割増賃金(時間外、休日、深夜)
どのような場合に対象となるの?
労働者と使用者が次の要件を満たす場合には「高度プロフェッショナル制度」を適用することができます。
(1) 労働者が、高度の専門的知識等を必要とし、その性質上従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められる業務のうち、労働者に就かせることとする業務
(2) 使用者との書面による合意に基づき職務が明確に定められていること。
(3) 年間の賃金が基準年間平均給与額の3倍の額を上回る水準以上であること。
(4) 使用者が労働者の労働時間を把握する措置を講じること。
(5) 使用者が労働者に対して、1年間で104日以上かつ4週間で4日以上の休日を与えること。
(6) 使用者が次のいずれかの措置を講じること。
ア.休息時間を確保し、深夜時間帯の労働回数の上限を定めること。
イ.一定期間の労働時間の上限を定めること。
ウ.1年に1回以上の2週間連続の休日を与えること。
エ.健康診断を実施すること
一定の収入ってどのくらい?
具体的な金額は、厚生労働省令で基準年間平均給与額(毎月勤労統計から算定される労働者1人当たりの給与の平均額)の3倍を上回る額とされており、少なくとも1000万円以上の収入を得ている人が対象となる見込みです。
職場のパワーハラスメントについて
- 2018年 10月 30日
そもそも「パワハラ」の定義って?
職場のパワーハラスメントとは、「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」と定義づけられています(厚生労働省 「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告」平成24年1月)。
どういう行為がパワハラになる?
たとえば、営業目標を達成できなかった社員に対して、罰ゲームとしてコスプレをさせて写真を撮影する行為などはパワハラに該当すると考えられます。
一般に、パワハラは、
(1)暴行・傷害(身体的な攻撃)
(2)脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言(精神的な攻撃)
(3)隔離・仲間外し・無視(人間関係からの切り離し)
(4)業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害(過大な要求)
(5)業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと(過小な要求)
(6)私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害)
の類型に分類されるといわれています。