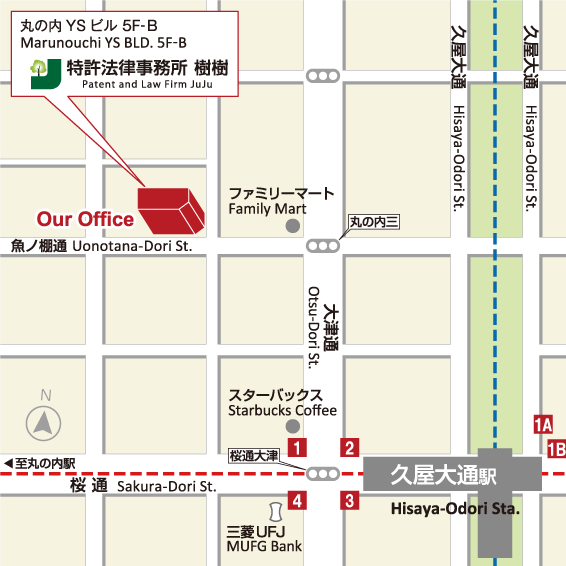印紙を貼らなければならない書類は何?
印紙を貼らなければならない書類は、法律で決まっています。具体的には、不動産の売買契約書、請負契約書、5万円以上(平成26年3月31日以前に作成したものは3万円以上)の領収書などです。
なお、印紙を貼る必要があるか否かは、書類のタイトルではなく、記載内容全体を踏まえて判断します。そのため、新しく作成した書類や、多数の人にほぼ同じ内容の書類を交付される場合などは、印紙を貼らなければならない書類か否か、念のため確認されることをお勧めします。
ひとまず200円の印紙を貼っておけば大丈夫?
貼らなければならない印紙代は法律で決まっていまして、書類の内容に基づいて金額が決定されます。なお、印紙税は、最低200円から最高60万円までの幅があります。
印紙の貼り忘れたら、どうなるの?
印紙を貼らなければならない書類に、適切な金額の印紙が貼られているか否かについては、税務署の調査対象に含まれます。そのため、税務調査の際、税務署から印紙の貼り忘れや貼るべき印紙の金額が不足していることを指摘されることがあります。
仮に、税務署から適切な金額の印紙が貼られていないことを指摘され、その指摘内容が正しかった場合、貼り忘れた印紙の金額若しくは貼るべき印紙の金額の不足分を追加で納付する必要があることはもちろん、ペナルティとして、貼り忘れた印紙の金額若しくは貼るべき印紙の金額の不足分の2倍の金額を納めることが必要になります。
自分の保管する書類だけに印紙を貼っておけば大丈夫?
印紙税は、書類の作成者に納付義務が課されます。そのため、誰が書類を作成したかが重要なポイントになります。
また、契約書などのように複数人で書類を作成した場合、書類の作成者全員が、全ての書類に対する印紙税を連帯して納付する義務を負います。そのため、書類の作成者のいずれかが保管する契約書に印紙が貼られていなかった場合、税務署は、印紙を貼って書類を保管していた書類作成者に対しても、印紙税とペナルティを納付するよう請求することができます。
したがって、複数人で書類を作成した場合は、すべての書類に印紙が貼られているか否かを確認することを強くお勧めします。