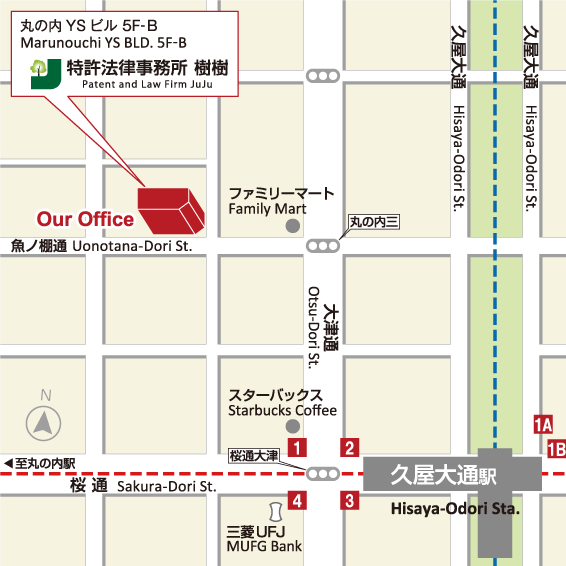韓国の特許の審査基準が改正され、7月1日から「コンピュータプログラム」という請求項が認められるようになった。
日本では「コンピュータプログラム」という請求項が認められているが、韓国では、これまでは、「コンピュータプログラムを記録した記録媒体」(CDやDVDなど)という形でしか認められてこなかった。今回の改正で、プログラムの保護の態様を拡大したことになる。
ただし、日本では、単純に「コンピュータプログラム」という態様を認めているのに対し、韓国では、「媒体に記録されたコンピュータプログラム」という表現を要求するようだ。
とすると、「媒体」の意味が問題となる。
ここで言う「媒体」が、単体の媒体(例えば、CD、DVD、コンピュータのハードディスクなど)を意味するのであれば、コンピュータプログラムという請求項を認めたとしても、その実質は、今までの「記録媒体」という請求項と変わらないのではなかろうか。これに対して、「媒体」が、複数の媒体でも良い(例えば、ネットワークで接続された複数のサーバなど)ということになれば、コンピュータプログラムという請求項の保護範囲は、今までよりも、かなり拡大されることになる。
いずれにしても、請求項の表現の範囲が広がったのは歓迎すべきことである。
実質的な保護範囲については、今後の実務動向を見極める必要があろう。
2014年7月
韓国でコンピュータプログラムの請求項が可能に(弁理士・弁護士 加藤 光宏)
- 2014年 7月 08日
「地域名+商品(サービス)名」=地域団体商標か?(弁理士・弁護士 加藤光宏)
- 2014年 7月 06日
地域団体商標という制度がある。いわゆる地域ブランドを守るための制度で、「地域名+商品(サービス)名」に商標登録を認めるという制度だ。
平成25年9月末時点で、551件の登録があるとのことだ。
愛知県では、「蒲郡みかん」「有松鳴海絞」などが登録されているし、東海地方で見ると、「静岡茶」「熱海温泉」「飛騨牛」「関の刃物」「松阪牛」「伊勢うどん」などが登録されている。
その一方で、喜多方ラーメンのように登録できなかったなどという例もあり(参考記事)、「地域名+商品(サービス)名」であれば、何でも地域団体商標として登録を受けられるという訳ではない。
地域団体商標として登録を受けるためには、
(要件1)組合などの団体が使う商標であること(一企業だけが使うものはダメ!)
(要件2)商品や主要原料の産地、提供地など商品(サービス)が地域と密接に関連していること
(要件3)上記の団体などが使用してある程度周知になっていること
(要件4)普通名称になってはいないこと
という条件を満たす必要がある。
有名な商標などでは、既に組合や団体以外の者も使用しているため、要件1を満たさなくなってしまうようだ(先の喜多方ラーメンは、このパターン)。特許庁による分析でも、地域団体商標が拒絶される事例の70%が、この要件を満たさないことによるものとされている。
さて、出願にあたって、気になるのが要件2だ。
地域と商品等との密接な関連というのは、いくつか例を見ればわかると思う。
例えば、
「和歌山ラーメン」は、「和歌山県産のスープ付き中華そばのめん」を指定商品として登録されている。
「姫路おでん」は、「姫路市におけるおでんの提供」を指定役務(サービス)としている。
「伊勢うどん」という商標は、「三重県産のうどんのめん」が指定商品だ。
個人的には、「伊勢うどん」というのは、あの太い麺と、濃いタレに特徴があり、それが伊勢地方発祥というだけであって、うどんの麺が三重県産かどうかということに は、あまり関係ないと思うのだが、地域団体商標の登録を受けるためには、指定商品を「三重県産」と限定する必要がある。仮に、この組合が、三重県外に、大きな うどん工場を作って、伊勢地方はもちろん、県外にも伊勢うどんを提供するようになったら、指定商品である「三重県産」の麺に対して商標を使用していないことになってしまうのではないだろうか。特許庁の審査基準を見ると、地域との関連については、「●●地方に由来した製法の××」という指定も認められているようだが、こうした指定も、「製法が異なったら?」という疑問はぬぐえない。
また、「姫路おでん」のように「姫路市におけるおでんの提供」という指定の場合、姫路市以外に全国ブランド化を図ることは困難なのではなかろうか?
地域団体商標が地域ブランドを保護するための制度であることを考えれば、地域との密接な関連を要求するのは当然のことである。しかし、逆に、地域名を入れた商標だからといって、必ずしも「産地」「提供の場所」「製法」などの意味で、地域と密接な関連があるとは限らない(名前をつけるときに、安易に地域名や自分の名字などを入れるのは、ありがちなことだろう。)。また、地域ブランドを、将来、どのように活用していくのかも考慮しなくてはならない。
本当に地域団体商標として登録する他ないのか?また、地域団体商標として出願する場合に、安易に「●●産の」等で指定をしてよいものか?
よく検討した方がよいかも知れない。