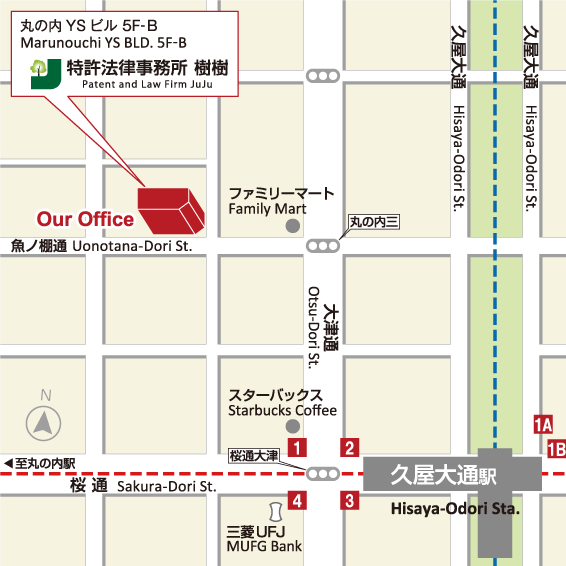平成27年3月13日(金)、職務発明制度の見直しを含む特許法の改正について閣議決定がなされた。
今まで、企業の従業員等が業務として完成させた発明(職務発明)は、従業員等のものとされていた(その後、企業に移転していた)のを、最初から企業のものというように扱いを変えるという内容だ。この改正については議論もあり、若干、右往左往した感もあったが、ともかく方向性が決まったことになる。
改めて改正内容を見てみると、上述の帰属の点については、
職務発明(特許法35条)において、3項に「…職務発明については…あらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは…発生した時から当該使用者等に帰属する。」とある。
もちろん、無償ではなく、4項において「相当の金銭その他の経済上の利益(次項及び第七項において「相当の利益」という。)を受ける権利を有する」と規定されている。
従来は、職務発明を企業に移転するのと引き替えに対価の支払いを受けるという枠組みだったのが、職務発明をしたら(無条件に企業に帰属するけど)、企業から相当の利益を受けることができますよという枠組みに変わったということになる。
従来は、対価を払って職務発明を「買っていた」のが、職務発明は最初から企業のものだから対価はいらず、ご褒美をあげればそれで良い、というように変わったのだ。当然、従業員に支払われる「相当の利益」とやらの金額は、低くなるだろう。
ただし、この対価の定め方について、合理的なものでないといけないですよ、という従来の規定は踏襲しつつ、6項で、「経済産業大臣は、発明を奨励するため、産業構造審議会の意見を聴いて、前項の規定により考慮すべき状況等に関する事項について指針を定め、これを公表するものとする」との規定が設けられた。
職務発明規定が合理的と言えるかを争った判例があり(東京地判平成26年10月30日(H25(ワ)第6158号))、今後も、就業規則等が「合理的」か否かは争点の一つとなる。
また、6項に定められた「指針」に準拠しているか否かも争点となる。
つまり、従業者は、就業規則等で「相当の利益」が定められているとき、それが合理的か?というハードルを超え、指針に準拠しているか?という第2のハードルを超えて初めて、その金額を具体的に争うことになる。
しかも、その金額は、発明の対価が基準となるのではなく、6項の指針に従って判断されることになろう。
この先、どのような「指針」が出されるのか。それが重要と思われる。