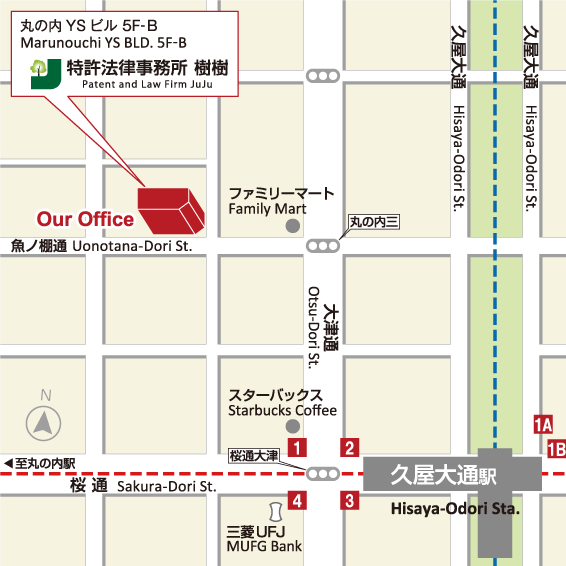【はじめに】
平成26年1月31日に日本弁理士会東海支部主催で「知的財産セミナー2014 -タイの知財丸わかり」が開催された。このセミナーは、
・タイ、インドネシアの知財動向
・特許セッション(出願、小特許、出願戦略等)
・商標セッション(出願、審査、識別力、周知商標等)
・権利行使セッション(刑事訴訟・民事訴訟の特徴、訴訟事例等)
の4部構成であり、筆者は権利行使のセッションを担当した。セミナーで用いた資料は、弊所ホームページ内の出版物/講演資料のコーナーにアップしてある。このブログでは、今後、数回に分けてセミナーで用いた資料の解説記事を掲載する予定である。
日本弁理士会東海支部では、上記セミナーに向けて、東南アジア委員会を立ち上げ、タイ・インドネシアの知財制度の調査研究を行ってきた。この活動では、はじめに種々の文献、資料、インターネット上の情報などを収集・検討し、疑問点を整理した上で、2013年10月に、現地調査として、タイの法律事務所、裁判所(CIPITC)、最高検察庁などを訪問し、ディスカッションを行った。上記セミナーには、これらのディスカッションを通じて得られた情報もふんだんに含まれている。ディスカッションで得られた情報等は、あくまでもディスカッションに応じていただいた現地の弁護士、裁判官、および検事の私見に過ぎない場合もあるため、記事の中では、ディスカッションで得られた情報を区別できるように気をつけたいと思う。
以下の記事に付した見出しは、それぞれセミナー資料の各ページのタイトルである。セミナー資料を片手にご覧いただければと思う。なお、ブログの記事においては、細かく参考文献などは提示しないので、その点も、ご了承いただきたい。
【タイにおける権利行使の方法】
知的財産権の権利行使の方法としては、裁判所での民事的措置および刑事的措置、税関での水際措置が挙げられる。民事的措置では、差止請求、損害賠償請求が可能である。刑事的措置では、侵害者に対して禁固・罰金などの刑罰が科されることになる。水際措置では、輸入時に侵害品が税関で差止められ、廃棄等される。
特徴的なのは、刑事的措置において、「経済的補償」が認められていることである。タイでは、著作権侵害については罰金のうち半額を、被害者に交付する制度がある(この制度は特許等にはない)。しかし、この資料で述べている経済的補償は、罰金の一部を被害者に交付するということではなく、知的財産の侵害によって被った損害の賠償を刑事手続きの中で請求することができる制度のことである(タイ刑事訴訟法40条~51条)。これは刑事的民事訴訟とでも呼ぶべき制度であり、法律上はあくまでも民事訴訟に分類されるものだが、検察官が被害者の代理人となって損害賠償請求手続きを遂行できる旨が規定されており、被害回復請求に対する判決は刑事判決の一部をなすという位置づけになっており、刑事手続と密接に関わった手続きとなっている。刑事訴訟を前提とする請求であるから、有罪のときにのみ損害賠償請求も認容され得るのであり、無罪判決のときには損害賠償請求も棄却されることになる。(←ここ、結構大切なところ!)
タイの最高検察庁の検察官は、この刑事的補償について、「被告人を有罪にすることに次いで、損害賠償請求することが検察官の重要な役割でもある。被害者に損害が生じていることが分かっている場合、検察官は、刑事手続において、その損害賠償を請求しなくてはならない。」と述べていた。
タイにおける権利行使は、全体の95%以上が刑事事件である。その理由は、いろいろとあるだろうが、上述の経済的補償が受けられることも一つの理由として考えられるのではなかろうか。
【タイにおける侵害対応関連機関】
タイにおいて知的財産権侵害に対処する機関としては、タイ税関、タイ経済警察、タイ商務省知的財産局、タイ検察庁知財専門部、タイ知的財産及び国際取引中央裁判所(CIPITC)、特別捜査機関が挙げられる。それぞれの機関の役割についての説明は省略する。
タイが知的財産権侵害への対策を進める契機となったのが、1995年のWTO TRIPS協定である。同協定では、加盟国に対し、知的財産権の行使について民事的措置、刑事的措置を整えることを要求しており、CIPITCやタイ検察庁知財専門部などは、この要求に応えるべく設立されたものである。
【タイ知的財産及び国際取引中央裁判所(CIPITC)】
タイの知的財産権保護において、中心的な役割を果たすのがCIPITCである。普通にシー・アイ・ピー・アイ・ティー・シーと読むしかない。略語にしても長い。それは、タイの人も感じているらしい。知的財産権関係の方は、「IP Court(アイ・ピー・コート)」という通称を使うことが多いとのことである。
CIPITCは、知的財産権等を専門に扱う裁判所であり、日本の知財高裁と似ている点もあるが、タイの法律上の位置づけは高裁ではなく一審の特別裁判所である。タイでは、知的財産権の民事、刑事事件は、全てCIPITCに係属する。そして、通常の事件は、日本と同様に三審制であるが、知的財産権事件は、一審がCIPITC、二審が最高裁という二審制となっている。
CIPITCは、三人の裁判官が審理に当たる。裁判官の構成は、二人が判事(Career Judgeと呼ばれる)、一人が補助判事(Associate Judgeと呼ばれる)である。補助判事は、エンジニア、技術の研究者、弁理士など、技術的なバックグラウンドを有している者がなる。このように、技術的なバックグラウンドを有する者が加わることにより、特許事件など技術的な理解が欠かせない案件にも対応できるようにしているとのことである。補助判事も裁判官の一人であるため、日本における専門員と異なり、判決に加わる。単に技術を判事に解説することだけが役割ではない。
CIPITCでの訴訟では、通常の訴訟手続と異なる固有の手続が設けられている。例えば、遠隔地にいる証人に対する尋問の便宜を図るためテレビ会議システムを利用した尋問が認められており、当事者の合意があれば証拠書類などもタイ語でなく英語で提出することができる。これら固有の手続きは、民事訴訟法、刑事訴訟法ではなく、「CIPITC設立および手続法」に規定されている。従って、知的財産権について訴訟を遂行する際には、同法の内容を確認することが必要となる。