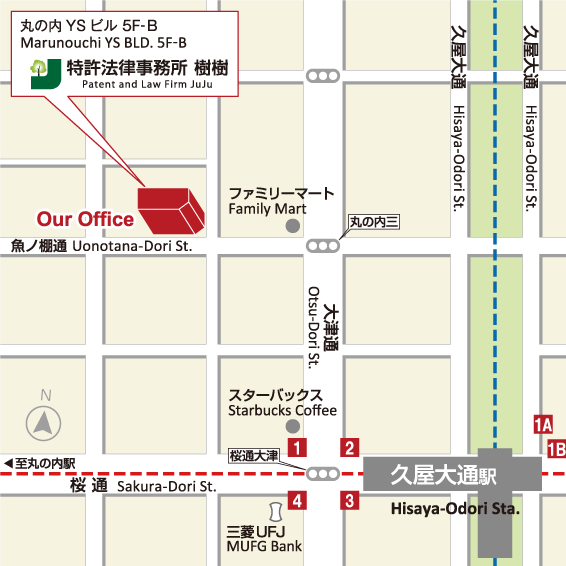今年は、意匠法の動向から目が離せない。
特許庁では、スマートフォンなどの画像について意匠登録を認める方向の検討を進めている。(関連資料)
ここで言う画像とは、例えば、汎用機のOSの画像、アプリケーション・ソフトウェアの画像、ゲームソフトの画像、アイコン自体、ウェブページ画像、壁紙画像などのことである。
米国、欧州、韓国では既にこれらに対して意匠権での保護が認められている。これに対して日本では、非常に限定的だった。やや粗っぽい表現になるが、機器に最初から組み込まれている初期画面については登録を認めるが、アプリケーションのように後からインストールする画面については登録を認めないというものである。これは、日本の意匠制度が「物品」のデザインという要件を重視してきたことによるものであるが、いかにも世界標準からすれば立ち後れた感は否めない。ここに来て、ようやく特許庁も、これではいけないと本腰を入れることになったのだ。
その方向性は、従来型の「物品」のデザインというカテゴリーに加え、情報機器の画像という新たなカテゴリーを設けるというもののようである。現状では、各業界団体から賛否両論の意見が出されており、収束までにはまだ時間を要するように見受けられる。
反対意見の一つには、情報機器の定義が不明確ではないか、将来的に情報機器が拡大し、広範に過ぎる権利が付与され得るのではないかといったものがある。意匠の類否判断や権利範囲をどうするかという観点からは、当然の意見である。
しかし、そもそも「情報機器」という枠組みに違和感を覚える。意匠の類否判断や権利範囲の議論と、保護対象の議論とは分けて考えた方がよいのではなかろうか。今やありとあらゆる機器が「画面」を持ち、ネットワークに接続される時代である。お掃除ロボットだって、そのうちにご主人様の後をついてくるペットアプリや、シューティングゲームのターゲットアプリ、ゴキブリ駆除アプリなどをインストールできるようになり、その画面について保護の必要性が出てくるかも知れない。現時点で世の中に存在する「情報機器」という物だけを前提に制度を考えていては、産業の変化のスピードにはついていけない。是非、先を見据えた議論を期待したい。
2013年3月
意匠法の動向に注目!(弁理士・弁護士 加藤光宏)
- 2013年 3月 28日